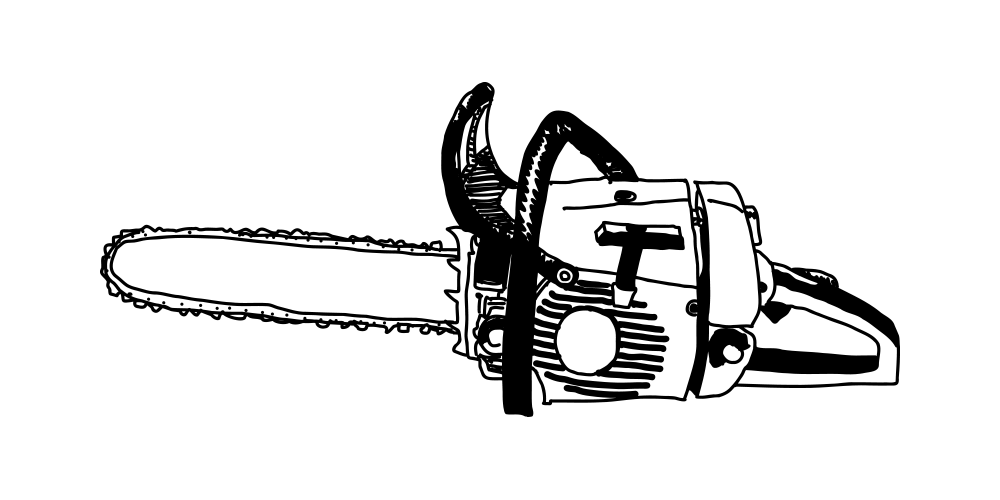二次燃焼方式
薪ストーブの問題点
二次燃焼方式薪ストーブ利用者からの声
二次燃焼方式のストーブが普及するにつれ、 薪を買いに来るお客から様々な苦情を聞かされます。
例えば
- とにかく燃やしづらく、ストーブや室内が温まるまで時間がかかりすぎる。
- うまく燃やせない時は前面の扉を開けるように言われたが、そうすると煙は室内に入っ てくるし、火の粉が飛び出し、火災になる危険を感じた。
- 燃やし始めに室内の窓を開けなければいけない。
- とにかく燃やしづらく、ストーブや室内が温まるまで時間がかかりすぎる。
- 灰を取り出すのがやりづらい。
- 勢いよく燃え上がっている炎を制御できず、怖い思いをした。
私の知人が30年以上前から薪ストーブを愛用し、7年ほど前に二次燃焼方式に買い替えたのですが、「以前よりも室内が暖まらなくなった。」と言っていました。二次燃焼方式に問題が有ることは明らかです。
二次燃焼方式薪ストーブ誕生の背景
二次燃焼方式が登場する前は、ほとんどのメーカーが同じ構造のストーブを作っていました。正面には窓ガラスの付いた大きな扉が有り、その下にはもうひとつ小さな扉が有りました。炉内には格子状の穴があるロストルが有り、この上に薪を並べロストルの下から空気を入れて燃やすのです。灰はロストルの穴から自然落下し、下にある受け皿にたまります。受け皿は下の小さな扉から取り出します。また、この扉が空気の取入れ口となっています。炉内は密閉されていて、真上に煙突が有るので、その吸引力によって空気は下から上へとスムーズに流れます。
各メーカーはそれぞれ安全で使い勝手が良く、そして暖房効果の高いストーブを追究してきたはずです。その結果まったく同じ構造となったのです。これは薪ストーブが完成域に達したことを意味しています。また、素材はどのメーカーも鋳物でした。これは、耐熱耐久に優れ、そして蓄熱性が高くストーブには最適だからです。
しかし、今店頭でこのタイプのストーブを見ることはありません。素材は鋼板で様々なタイプの物が並んでいます。これは、業界全体が、今までの主役を排除し、見た目はカッコ良くそして高価な二次燃焼方式へとユーザーを誘導しているのです。
製品が完成域に達したとき、ユーザーにとってはありがたいのですが、メーカーにとっては最悪なのです。新たな製品を開発することはできず、残るは価格競争だけです。こんな状況がこの先ずっと続くと思った思ったとき、経営者たちはいたたまらなかったでしょう。そして、性能を少々落としてでも、新たな、付加価値の高い製品を作ろうとしたはずです。そして登場したのが、触媒方式と二次燃焼方式です。
触媒とは、自動車の排ガスのように有害物質が含まれる場合、触媒と化学反応をさせて無害にする装置です。薪を燃やして有害なガスが出るなどと聞いたことがありません。また、二次燃焼は焼却炉のための技術です。焼却炉の場合は一度に大量のゴミを燃やすので、酸素不足となって煙が出ます。この煙だけを再度燃やす二次燃焼装置が必要なのです。薪ストーブの場合は空気の取入れを調節するだけで簡単に完全燃焼できます。煙りなど出さないで燃やせるのです。
要するに触媒方式も二次燃焼方式も薪ストーブにはまったく必要がないのです。これらの無駄な装置が付くことで取扱いは難しくなるし、炉内の空気の流れが悪くなり薪をうまく燃やせなくなります。特に二次燃焼方式は煙りを燃やすことが目的なので、煙りを出すためにロストルを無くしたのですから、更に事態を悪化させたのです。このため冒頭のように苦情が多発しているのです。
二次燃焼方式薪ストーブの宣伝文句はデタラメ
触媒方式はそれほどヒットしませんでしたが、二次燃焼方式は大ヒットしました。それは店員の「煙りを再度燃やして、排ガスをクリーンにし、また、燃焼効率を上げて暖房効果を高めています。」という宣伝文句にほとんどのお客は納得してしまうからです。しかし、この宣伝文句はデタラメなのです。
石油ストーブやガスストーブでは、最大出力〇〇Kcal/Hとか燃焼効率〇〇%などと表示されていますが、ユーザーも実際に使ってこの数値と同程度のことが再現できます。ですから、科学的に正しいデータとして、ユーザーは性能を比較することができます。
ところが、薪ストーブの場合はまず燃料となる薪の成分が一定ではありませんし、燃やし方も人それぞれです。再現性が全くないのです。ですから性能に関する科学的に正しいデータはないのです。そもそも薪ストーブは煙突を含めて巨大な装置なので出力などのデータを計測すること自体不可能でしょう。ですから燃焼効率を上げたとか、排ガスをクリーンにしたとか言う宣伝文句はすべてデタラメなのです。
二次燃焼方式薪ストーブの弊害
10年ほど前、それまで室内の煙突はシングル煙突でしたが、突然一斉に断熱材を巻いた二重煙突が使われだしたのです。ここは放熱して室内を暖める所でもあるし、また、煙突が245℃以上になると煙道火災の危険があるので、温度計を取り付け温度管理する所なのです。しかも値段は1本3千円ほどだったのが、3〜5万円もするのです。この様なひどい事をした理由は二次燃焼方式は燃えが悪いので、少しでも煙突の吸い込みを良くしようとしたからです。
また、二次燃焼方式は一次で煙りを出すように燃やし、二次でその煙に上から空気を吹きかけて再度燃やすため、空気取入れ口が2カ所あり、レバーで操作するのですが、取入れ口がどこにあってどのくらい開いているかが全くわからないのです。ですからレバーに不具合が生じていてもそれがわからず、勢い良く燃え上がる炎を制御できなくなってしまうのです。
二次燃焼方式は室内の空気を大量に取り込んでしまうのです。そこで外気導入という手段を取らざる得ないのです。ストーブ本体後ろに空気取入れ口があり、床に穴を開けパイプで外気を取り込むと言った工事が必要なのです。日本ではこの工事をするケースは少ないのですが、このため暖房効果は上がらないし、室内の酸素不足をおこす心配があります。
焼却炉の構造は完成域にあったかつての薪ストーブと全く同じです。ロストルがあって、密閉度を良くし、そして真上に煙突を付けるこの構造は物を燃やすのにベストなのです。ロストルがないと燃やしづらく、炉内の温度がなかなか上がらず長い時間煙りを出し続けるでしょう。排ガス規制のある焼却炉ではこの様な物は全く売れないでしょう。
ところが、薪ストーブには規制がありませんから、どんなに煙りを出しても許されるのです。二次燃焼方式に二重煙突そして外気導入はいづれもユーザーにとってはデメリットなのですが、それらは新しい技術で性能をアップさせたとデタラメを言っているのです。ユーザーは混乱するばかりです。
理想的な薪ストーブとその使い方
薪を燃やす作業は単純で簡単なことです。今までの知識や経験から理想的な薪ストーブは容易に導き出せます。薪ストーブは燃焼中、室内の空気を引き込みながら煙突から大量の熱量を放出しています。これは大きなロスです。特にせっかく暖めた空気を外に出してしまうことが暖房効果を下げる一番の原因です。ですから最も少ない空気で薪を完全燃焼できるストーブが最も暖房効果が高いと言えます。これは最も薪を燃やしやすいストーブとなるでしょうし、それはロストルがある完成域に達していたかつてのストーブなのです。
薪ストーブで快適な空間を得るには、薪の選択が重要です。薪にとって一番の敵は薪に含まれる水分です。普通に乾いた薪で1kgの中にコップ一杯ほどの水が含まれています。これが気化するときに大量の熱量を奪い暖房効果を下げます。また、煙りを多く出し煙突を詰まらせることになります。ですから、薪の水分をできるだけ除去することです。そのためには薪を細く割ることです。
私が使っている薪はカラマツで長さ30cmです。太さは片手で握れる物から片手では10cmほど余るような太い物まで様々な太さを燃やし比べています。
煙突の立ち上がり30cmの所に米国condar社製「CHIM GARD」という温度計をビス止めしてあります。この取説によると110℃〜245℃が安全な温度だと言っています。110℃以下だと不完全燃焼しやすく、245℃を超えると煙道火災の危険があると言っています。
この温度計を見ながら空気の取込口を調節するのですが、燃やし始め取入口を全開にし、ロストルの上に半分にした新聞紙をその上にたきつけと細く割った薪を乗せ、新聞紙に点火します。扉を閉めると同時にロストルの下から空気が吹き上がるのがわかります。10秒もすればボーボーと音を立て炎が燃え広がっていきます。適当に薪を足しながら炎がほど良い勢いで上がるように空気を調節します。4〜5分で温度計は200℃に達します。この温度計は板バネ式で急激な温度変化にはついていけません。実際には1〜2分で200℃に達しています。200℃になってからは245℃を超えないように空気を調節します。ストーブ内全体で炎が燃え上がっています。しばらくこのままストーブ本体が暖まるのを待ちます。15分くらいでストーブ本体も200℃を超えてきます。そして室内が適温になったら空気を絞り煙突の温度110℃〜150℃を維持します。この時太い薪なら2本、細い薪なら2〜4本が熾火の上に並べて置きます。炎は部分的にユラユラと上がっています。煙突は150℃以下でもストーブ本体は250℃ほどを維持しています。本体の温度を計る時は放射温度計を使って煙突が立ち上がっている近くのトップ面で計測します。
煙突の温度が低いほど煙突から放出する熱量は少なく経済的なのです。そして細い薪ほど水分が少なく燃えやすいので空気を最小に絞って燃やすことができます。室内は居心地の良い状態が維持できます。逆に太い薪は水分が多く燃えにくいので、空気をたくさん入れて高温で燃やすしかありません。煙突から無駄に放出される熱量が増え燃費は悪くなります。そしてストーブの前に立つと顔ばかりは暑すぎるほどになるのですが、足元はストーブに空気をたくさん吸い込まれスースーしていて居心地は悪いです。
ロストルの上に薪を置き下から空気を入れて燃やすことは基本中の基本です。そして密閉された中で燃やすのですから火の粉が飛び出ることは絶対に有りません。室内の煙突はシングルでそこで燃やし過ぎ、さらには煙道火災が起きないよう温度管理をします。天井など煙突が貫通する部分は引火しないよう二重煙突にします。これで安全面は完璧です。
正常な薪トーブのすゝめ
この薪ストーブの有り様は正常で何十年と続いてきたのです。これを否定する二次燃焼方式は狂っているとしか言いようが有りません。室内の煙突を二重にし温度管理をできなくさせ、一度にたくさんの薪を高温で燃やす様指導しています。これでは煙道火災を起こさせるようなものです。実際、煙突から火の粉が飛び出しているのを見たと言う情報が複数きています。また扉を開けて薪を燃やすなど超危険です。正常な薪ストーブなら扉を閉めた状態こそ密閉され空気の流れが良くなって良く燃えるのです。また、二次燃焼方式は薪を積み上げて最上部を点火すると聞いたのですが、これも道理を無視した狂った話です。
狂った状況を正常に戻さなければいけません。これから薪ストーブを購入する人達は正常な道を選択すべきですし、すでに二次燃焼方式を設置し、室内の煙突を二重にさせられた人達は、煙突はシングルにそしてストーブは正常なものと替えた方が、今後の薪代などを考えると得策だと思います。
しかし、今店頭にはこの正常なストーブはありません。カインズには、日本のメーカー(株)ホンマ製作所のカタログがあります。この中のHTC-60TXというストーブが有ります。現在私が使っているストーブです。それ以前はヨーロッパの老舗ドブレーのストーブを使っていましたが、比較すると(株)ホンマ製作所のストーブは非常に優れていてドブレーより数段上です。6年ほど前に買ったのですが、値段は8万円ほどでした。
薪ストーブ店へ行くときは、このカタログを持ってHTC-60TXを設置してほしいと言うのです。店側は「なぜそれがいいのか?」と聞いてくるでしょう。そうしたら「私は鋳物製でロストルの有るストーブが欲しいから」と言うのです。薪ストーブの事を知っている者ならば、鋳物とロストルを否定する人はいないでしょう。